企業の中には、Slackを社内Wikiとして活用しようと思われている方もいるのではないでしょうか。社内Wikiの導入は、下記の記事で説明している通り、企業に数多くの利点をもたらします。
・社内Wikiとは!?情報とナレッジ共有が容易にできる企業を目指す
しかし、ツールはランニングコストがかかりますし、制作には初期費用が必要です。そのため、費用負担を抑えるために、Slackを利用する企業も少なくないでしょう。
今回は、Slack の基本情報や社内Wikiとして利用するメリットなどをご紹介しますので、導入を検討している方はぜひ参考にしてください。
Slackとは!?
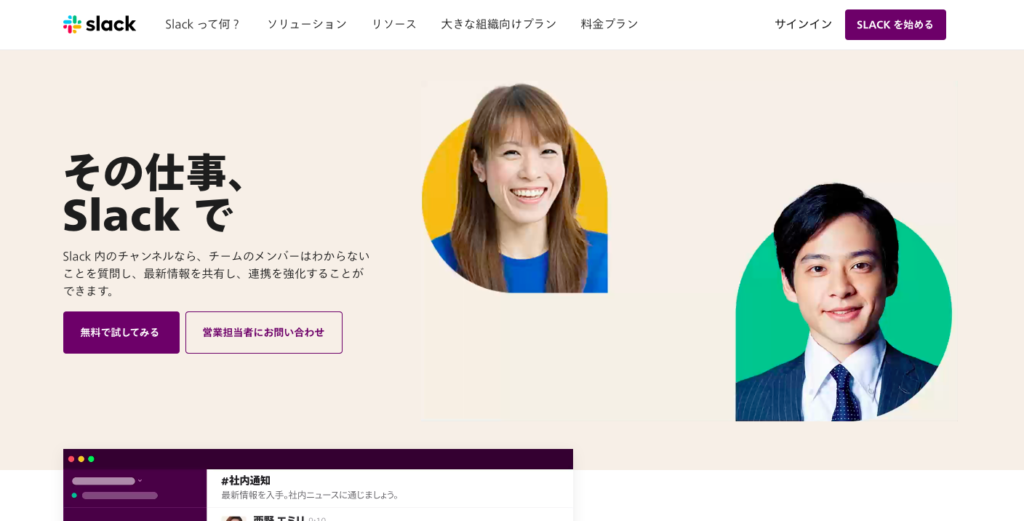
Slackとは、米国のSlack Technology社が開発・運営を行っているビジネスチャットツールです。Slack Technology社はGlitchというゲームの映像配信サービスを提供しており、もともとは自社のコミュニケーションツールとしてSlackが使用されていました。そして、それを商用化し現在サービスの提供を行っています。
Slack Technology社は2019年アメリカの株式市場に上場しています。また、孫正義氏が代表を務めるソフトバンクグループが出資をしており、日本でも非常に注目されている企業です。
すでに、Slackを導入している企業は非常に多いです。下記が導入している代表的な日本の企業になります。
・NIKKEI
・SoftBank
・三菱重工
・リクルート
・Yahoo Japan
・サイバーエージェント
・Panasonic
・メリカリ
・DNA
・mixiなど
すでに75万社の企業がSlackを導入しています。また、無料プランから大きな組織向けのプランもあり、企業の規模に関係なく多くの会社が利用しやすいサービスです。
社内Wikiとしても使えるSlackのメリット

社内Wikiとしても利用できるSlackにはさまざまなメリットがあります。これを見ればなぜ注目されているのかが一目瞭然です。
自然に生産性が上がる
1つ目のメリットは生産性の向上です。通常、グループチャットを行う場合、誰かがメッセージを送信したら、それに対して返信するのが一般的になります。しかし、Slackにおいてはメッセージを送信しても受信者側は返信する必要がありません。なぜなら、メンバーに必要な情報を伝えることが目的だからです。返信することに対する要求は行われないため、情報共有の際の手間を少なくできるでしょう。
また、ビジネスメールをするときによく使う言葉を省略することができます。例えば、下記のような言葉が代表的な例です。
・「お世話になっております。」
・「何卒よろしくお願いいたします。」
・「○○○株式会社 ○○様」
このような言葉はメッセージを送信するたびに使わなければならないので、生産性が下がります。一方、Slackはこのようなビジネスメールの礼儀を省略することができるので、伝えたい・共有したい情報だけを送信することが可能です。そのため、生産性の向上を期待できるでしょう。
さらに、メッセージを編集する機能もあります。間違えてメッセージを送信した場合、もう一度作り直して再送する必要がありません。送信したメッセージに直接変更を加えるだけなので、この機能も生産性の向上に一役買っていると言えるでしょう。
新メンバーの人にもすぐに情報を共有できる
2つ目のメリットは新メンバーへの情報共有が容易な点です。過去にやり取りしたコミュニケーションはすべてメッセージとして残されます。そのため、新たなメンバーが加入した場合でも、既存のメンバーの方が仕事に必要な情報を細かく教える必要がありません。過去のメッセージを見て必要な情報をすべて把握することができるので、プロジェクトメンバーの移り変わりが激しい企業でも利用しやすいです。
パワフルな検索機能
3つ目のメリットは強力な検索機能があるということです。Slackにはフィルタリング機能があり、日付や人、チャンネルを指定して細かく検索することができます。例えば、「#Aプロジェクトのチャンネルで2020年1月〜3月に投稿された○○さんの投稿」というように条件を絞り検索結果を取得することが可能です。強力な検索機能により、過去のメッセージを永遠と見返すというような作業をすることなく、必要な情報を素早く獲得できるので非常に便利な機能となっています。
さまざまなデバイスに対応
マルチデバイスに対応できるという点もメリットです。ブラウザやデスクトップアプリ、スマホアプリが提供されており、さまざまなデバイスで利用することができます。これにより、社外でも必要な情報を取得したり、伝えたいことをメッセージで送信できたりするのでリモートワークでも活用しやすいでしょう。
社内WikiをSlackで管理する方法

Slackには、さまざまな機能が搭載されているため、企業はあらゆる目的で活用することができます。そのため、実際に企業の中には社内Wikiとして活用しているところも少なくありません。ここでは、社内WikiをSlackで管理する方法を詳しく解説しますので、どのように社内Wikiとして使ったらいいのかわからないという方はチェックしてください。
スター機能を活用して社内Wikiとして使う
スター機能を利用することで、社内Wikiを管理することができます。重要なメッセージに対してスターを付ければ、すぐに見返せるようになります。スター機能は個人ごとに管理するため、社員に応じて重要なメッセージなのかそれとも不要なのかを選別することが可能です。
見返す際はスターマークをクリックするだけでスターを付けたコンテンツを表示させることができます。これを利用すれば、社内Wikiとしてメッセージを管理することができるでしょう。
ポスト機能を利用する
2つ目の方法はポスト機能を利用することです。ポスト機能を利用することで、ひとつのドキュメントとして情報をまとめておくことができます。また、チャンネル内で公開すれば、メンバーとドキュメントを共有することが可能です。この機能を利用すれば、まるで社内Wikiのコンテンツのように情報配信することができるでしょう。
現実的ではない!?社内WikiとしてSlackを使うデメリット

Slackは社内Wikiとして使うこともできますが、本来はビジネスチャットツールとして使われていますので、社内Wikiに必要な機能がすべて搭載されているわけではありません。そのため、社内Wikiとして運用するといくつかのデメリットが生じます。
過去の情報を見つけるのが難しい
過去の情報を見つけるのが難しいという点はデメリットです。たしかに、パワフルな検索機能が搭載されているため、それを駆使すれば過去に配信された必要な情報をつまみ出すことができるかもしれません。しかし、メッセージとして管理されるSlackは情報が膨大になりやすく、うまく検索できない場合、過去の情報を容易に見つけられない可能性があります。
情報をまとめるのが容易ではない
情報をまとめるのが容易ではありません。ポスト機能によりドキュメントとして情報を共有することができます。しかし、Webページとして配信される社内Wikiに比べて扱えるコンテンツ(画像、音声ファイル、動画)が少なく、細かい文字の装飾もしづらいため、情報を見やすくまとめることは難しいです。
まとめ
今回は、社内WikiとしてSlackを使う方法をご紹介しました。たしかに、工夫をすればSlackを社内Wikiとして使うこともできますが、運用していると不便な点も発生します。
もし、社内Wikiの導入を検討しているなら、「KYO-YU」の利用がおすすめです。KYO-YUは社内Wikiを構築できるサービスで、初期費用のみで導入することができます。また、オリジナル機能を付け加えることができたり、ランニングコストを削減できたりするので、安い費用で御社に適した社内Wikiを導入することが可能です。興味のある方は下記のお問い合わせページからサービスの詳細を伺ってみてはいかがでしょうか。


